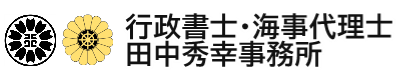遺言は、ご自身の死後に財産をどのように分けたいか、誰に何を遺したいかを法的に明確にする重要な意思表示です。遺言がない場合、相続人全員での遺産分割協議が必要となり、意見の相違から争いが生じる可能
相続

人が亡くなった場合、法律上は死の瞬間にその方の財産と債務(借金など)の双方が相続人に相続がされたことになるとされています。
その後行われる相続手続では、まず遺言書の有無を確認し、次のような形で「誰がどれだけ相続したか」を明らかにします。
・遺言書が残されていた場合:原則として遺言書で指示された故人の意思通りにそのまま財産の分配が行われます。ただし、必要があれば下記の遺産分割協議が行われる場合もあります。
・遺言書が残されていない場合:民法が定める相続人(法定相続人)が民法の定める割合(法定相続分)で財産を相続をします。ただし、具体的に誰がどの財産を相続するかは、相続人全員の話合い(遺産分割協議)によって決まります。
なお、相続人になっていても、例えば借金を相続したくないなど、相続を望まない場合は、相続を放棄することができますが、これは相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。
.png)
上記のような流れで相続手続は行われますが、実際には戸籍調査による相続人の確定、相続財産の調査・評価、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・分配、不動産の名義変更、相続税の申告・納付など行うべきことが非常に多くあります。
これらの手続は複雑で専門知識を要するため、行政書士など専門家の援助を受けることが有利です。当事務所では、提携する税理士・司法書士などと連携しながら、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続きまで、相続手続き全般をサポートし、円滑な解決に導きます。